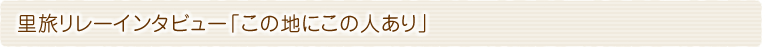
 |
|

今回は株式会社みの谷代表取締役 蓑谷雅彦様にお話しを伺いしました。株式会社みの谷は明治29年にろうそく、ランプなどの灯りやエネルギーの元になるものを取り扱い始め、現在ではガソリンスタンドやホテル、保険、不動産を中心に高山で事業展開している高山市経済の中心的な存在です。また、会社代表としてのお仕事のほか、高山商工会議所副会頭、飛騨・高山観光コンベンション協会の副会長などの役を持ち、高山地域の繁栄へ力を注いでいらっしゃいます。
飛騨・高山の魅力は?
高山は『人』が一番の魅力!!実は、私は20年前まで東京の保険会社でサラリーマンをしていました。比較するつもりではありませんが、飛騨高山の“人の良さ”に私はいつも“ありがたさ”を感じています。表現が難しいのですが・・・例えば、誰かと仲良くなるとその相手に対してガッツリ関わりを持ち、「あいつが言うのだったら一肌脱いでやる!」そんなやりとりが多くありますよ。それに、“自分が、自分だけが”と自分ばかりを押し出す人が少なく“飛騨高山を良くしていきたい”“飛騨高山が好きだ”“飛騨高山のために”という考え方の人がとても多いんです。この人柄の良さはず~っと昔からのもの。私の親父も「どうしてそんなに好きになれるの?」と思う程とにかく地元が大好きでした。結局、私もその背中を見ていたからか、親父と同じ路線になっているんだろうなと思います(笑)。特に公益社団法人高山青年会議所、高山商工会議所青年部会の活動は目を見張るほど活発です。何事にも積極的な彼等の姿勢は自らの手で良い街を作っていこうとする強い気持ちの表れで、今の高山の活気の原動力になっていると思います。
ここにいると、学生時代、サラリーマン時代の古い友人、当時のお客様から「今度高山に旅行に行くけど、良い所を教えて?」など今でも連絡をいただけます。知り合いの方に偶然お会いできるなんてこともあったり。“人の繋がりが自然に生まれる”のは飛騨高山だからこそではないでしょうか。このように、飛騨高山にたくさんの人が来てくれること程ありがたいことは無いですね。親父がしょっちゅう言っていた『高山が良くならなければ、高山にある多くの会社が良くなるわけがない』という言葉。これも本当に実感しています。
魅力と言えばもう一つ、食文化はどうしても外せません。『どうしてこんな山の中でこんな美味しい海の幸が食べられるんだ』って地元の自分でも思いますよ(笑)。年末年始においしい“ぶり”が食べられるのも、江戸時代の当時の偉い人に美味しいものを召し上がっていただくという目的でできたぶり街道のおかげ。本当にありがたいですね。

【ホテルACTY】
力を入れていることは何ですか?
基本的には“おもてなし”に力を入れています。自社のサービスでいえば、ガソリンスタンドなら、夏は冷たく冷えたおしぼり、冬は暖かいおしぼりで室内などを拭けるように、ちょっとしたことからできるサービスを地道に展開しています。ホテル(アクティ)なら、地元情報誌を宿泊のお客様にお渡しすることで、なるべくHOTな情報を積極的に提供できるようなコミュニケーションを心掛けています。また、私は“自然エネルギーのまちづくり検討委員会”のメンバーでもあり、高山市のエネルギー地産地消を目指しています。なかなか難しい面もありますが、高山でエネルギーの自給ができたらこれほど強い地域はどこにも無いと思います。
観光で高山へいらっしゃる方へ一言お願いします。
是非、高山の人と触れ合ってみてください!触れ合うことで良さがもっとわかってもらえると思います。私の場合は、観光に行くとレンタルサイクルに乗ってまちを回ってみたり、その土地の人と積極的に会話をしたりします。他愛もない会話から人間関係が始まり、互いの気持ちが伝わり合います。これってシンプルですが、その土地を知ることができますし、旅も楽しめるんですよね。皆さんも是非、高山にお越しの際は人との触れあいを存分に楽しんでみてください。
- 株式会社みの谷
- 住所 岐阜県高山市花里町4-78
- 0577-32-1100(代) / FAX:0577-35-1100

 |
|

今回は、有限会社原田酒造場 代表取締役原田勝由樹様にお話をお伺いしました。 江戸時代1885年から続く酒蔵の原田酒造店では杜氏・蔵人は全員飛騨人という陣営で飛騨の酒の味を守り続けています。襲名された“十代目打江屋長五郎”という名跡や店内に飾られている先祖が使用していたという江戸時代の武具などからも山車蔵元の長く由緒ある歴史を感じます。
飛騨・高山の魅力は?
高山は『酒がおいしい!』と全国のお客様からお褒めの言葉をいただきます。高山の良質な水と寒暖差が“良質な米”を育て、それが酒造りにとって恵まれた環境となっています。歴史的にも高山は江戸と堺の真ん中に位置していたため、東西の酒造り文化の融合地となっていました。また、高山は徳川幕府の直轄地だったため、江戸の役人からいち早く近代的な酒造りの情報が入ってきたことも酒造りの発展に功を奏したようです。そして、昭和30年代終わりのディスカバージャパンのキャンペーンで高山の酒がもつ独特のコクが全国的に注目されたのをきっかけに、飛騨高山はおいしい酒どころのイメージが定着しました。
当蔵の味はというと、全体的に豊潤ですっきりしているところが特徴で、“フルーティなお酒はすっきり”“辛口のお酒は透明感”を大切にしています。当蔵では13年程前“花酵母”という花の蜜から採取する酵母を取り入れました。さすがにお酒から花の香りがするわけではないですが、花酵母は原料のお米が持つフルーティな香りや、豊かでなめらかな味わいを引き出し、日本酒をよりおいしくしてくれます。また、夏は爽やかに、秋は熟成した旨味などが楽しめるようにと、お酒を通して季節感を味わえるような酒造りを心掛けております。
高山の秋の楽しみ方は?
高山の秋は楽しみがたくさんありますが、やはり、地元食材を地元のお酒で楽しまれるとより高山の秋を感じていただけると思います。中でも秋に一番お勧めなのがきのこ類。おそらく高山でしか食べられないキノコがたくさんありますから、ぜひお酒とともに試していただきたいですね。“タイコノバチ”というキノコは味噌で炒めるととても美味しく地元の人は大好きです。落ちアユの塩焼きなんかは今の時期が最高です。また、そろそろ紅葉も始まるので名所にドライブに行っても素敵な景色を眺める事ができそうです。

力を入れていることは何ですか?
酒造りに関しては、新製品の開発をどんどん進めています。また、お酒以外の分野でも高山の酒蔵だからこそできる食品の開発に力を入れています。例えば、地酒アイスは今年の夏の新製品ですし、酒粕とお酒を組み合わせた飛騨牛地酒カレーというものも開発しました。元祖地酒チーズケーキバーという商品は本当に多くのお客様にお買い求めいただいています。山車の総本店という特別な場所にわざわざ遠方から足を運んで下さるお客様には、ここにしかない特別なものを提供することで高山をより一層好きになって頂き、当蔵のお酒を飲んでくださっているお客様には、より一層うちのお酒のファンになっていただきたいですね。
観光で高山へいらっしゃる方へ一言お願いします。
飛騨高山は「江戸文化と京文化の融合で培われた土地」という背景を感じながら、古い町並みや東山寺院群等で歴史文化に思いを馳せていただけたら良いと思います。山の中の町なのに意外にも江戸時代から親しまれている魚介料理があるなど、食文化探索という視点だけで散策しても、高山ならではの面白い発見があるかと思います。一度で全てを体験するのは難しいと思いますので、「食文化」、「歴史」、「癒し」などのようなテーマを設けて訪れてみてはいかがでしょうか?飛騨高山は何回訪れても十分楽しんでもらえる魅力がある場所ですよ。
- 有限会社原田酒造場
- 住所 〒506-0846 岐阜県高山市上三之町10番地
- 0577-32-0120 / FAX:0577-34-6001
- http://www.sansya.co.jp

 |
|

高山の歴史には、金森氏時代(1586年~1692年)とその後の幕府直轄地(天領)時代という歴史的背景があります。角正(かくしょう)様は高山の歴史と深い結びつきがあり、200年以上精進料理を継承されてきた岐阜県で最も古い料亭。高山の武家屋敷街の一角にある建物は250年を超える趣深い佇まいで、敷地の中の全てが市の重要文化財でもあります。今回は角正12代目当主の角竹正至様にお話しをお伺いしました。
飛騨高山の魅力はどんなところですか?
私どもの先祖は江戸の郡代役の御付の料理人でした。江戸から一緒にこの地にやってきましたので、元を辿れば、実は私どもの料理は江戸の料理だったようです。当時は高山にいながらにして鯛や平目、鱒など、この土地以外の食材で料理をしていました。当時の“ご馳走”という言葉は“馬に乗って走り回り、食材を探すこと”が本来の意味としてありますから当然なのかもしれません。
当時は、武士は武家屋敷街、町人は町人街と住居地区域が定められていましたので、料理屋となれば商家に当たるところですが、角正は武家屋敷街に居を構えていました。おそらく御付きの料理人ということで、このような特別な場所が許されたのではないでしょうか。また、料理人として郡代家だけでなく、その家来の料理も賄わせてもらっていたようで、そのお料理に使用したのがアユやタケノコ、マツタケなどの飛騨高山の土地の食材でした。
また、今では飛騨牛は当たり前のように使用されていますが、もともと料亭ではすっぽん以外の四足は使ってはけないという文化もありました。現代の料亭の魅力というのはその土地のものをどれだけおいしく提供できるかに変わってきていています。このように、私たちはだんだんと変化していく時代の流れに沿いながら、できるだけこの飛騨高山の文化を良い形で残したいと思っております。
そして、高山には外国人観光客がすごく多いですね。あくまで私見ですが、高山の歴史的な風景や風習が魅力に映っているのなら、あまり外国人の好みに合わせようとせず、自信を持ってありのままの日本、ありのままの高山をアピールできたら、グローバル化が進む現代でも日本文化が認めてもらえるのではないでしょうか。“昔のままを遺す”ことで“古い町・歴史の町高山”としてグローバルに通じていけるような気がします。その観点から見ると既に高山は町や景色の保存・維持に力を入れており、歴史を貴重な財産として守っていることに魅力を感じています。
力を入れていることは何ですか?
角正においては12代続いた伝統を受け継ぎ、私ども自身も魅力にならなければならないと思い日々努力を続けています。例えば、当店の建物や造りなどはできるだけ原型をとどめた状態で残していきたいと思っています。建物も庭も当時のままですから、私どもの建物を介して当時の建築技術も残していけますし、研究もできます。
外国人のお客様には、当店では食材の説明に困らないレベルでの英語対応もしています。当店にお越しいただける外国人の中には、日本中を旅行してきた最後に立ち寄りいただく場所が高山で、私どものお店ということもよくあります。日本文化に精通されている方も多く、基本的にはお箸に困られるようなことはないです。その方々に日本での最高の思い出が高山であり、当店で最高に良い食事を味わっていただけるよう、きめ細かいサービス “言葉にならない”サービスを提供していきたいと思っていますし、『ここが日本で一番喜んでいただける場所』を目指す意気込みでやらせてもらっています。
観光で高山へいらっしゃる方へ一言お願いします。
高山にいらっしゃったら体験していただきたいことは、せっかくこれだけ古いものが残っていますので、少しでも触れていただきたいですね。多くの人が『古いものが良い』と思っているのは何故でしょうか、そんなところに着目していただいて、建物を見ていただいたくといかがでしょうか。古いものは不便だったりもしますけれど、江戸時代がなかったらこの建物や文化は育まれなかったんですね。当時にさかのぼって、「なぜ、江戸時代にこうなったの?」と想像しながら、壁のひとつにも意識することで見えてくるものが全く違ってくると思います。
昔の建物には縁側の素材、天井の板の素材、壁の色全てに意味があり、当時の格式に基づいた内装などがあることなども知った上で歴史を感じることができたら、高山がより一層魅力的になると思いますよ。


【高山市重要文化財の庭】
ゆったりと食事をしながら四季折々に表情を変える庭を楽しめます。
- 精進料理 角正
- 住所 〒506-0838 岐阜県高山市馬場町2-98
- 0577-32-0174
- 通販ページ : http://www.kakusyo.com/

 |
|

株式会社打保屋様が高山の地で駄菓子の製造販売を始めたのが明治23年。雅俊社長の祖母セツさんが高山に初めて砂糖を持ってきたと言われており、それが「打保屋商店」の始まりである。昔から「打保屋さん」の愛称で知られていたため、平成17年社名を株式会社打保屋に変更。創業開始から常に高山の歴史とお客様に寄り添ったスタイルで飛騨駄菓子を作り続けています。
飛騨高山の魅力はどんなところですか?
駄菓子とは“その地域で独特の発展をしたもの”という定義がありまして、飛騨、播州(兵庫県)、仙台の3か所に駄菓子文化が根付きました。飛騨は木の実や穀物が豊かな土地だったためか、飛騨駄菓子の原料は主に大豆と胡麻、落花生が使用されています。
例えば、飛騨駄菓子の中でも最も歴史が古いと言われている“こくせん(穀煎)”というお菓子。現在はゴマで作っていますが、昔は稗や粟などいろいろな穀物と水あめを合わせていたそうです。
“三嶋豆”という大豆に砂糖をコーティングした駄菓子は高山発祥と言われており、開発者である三嶋さんが歯の悪いお母さんでも食べられるような駄菓子として開発したものです。大豆はただ炒っただけではそれほど柔らかくはならないのですが、豆を水に漬け、ふやかしてから炒ることで豆が噛みやすくなり、カリッとした触感に仕上がります。それを甘い衣でコーティングすることでおいしく食べてもらえた。という母を思う心から誕生した駄菓子なんです。
明治の初めには豆に味をつけたお菓子はなかったそうで、三嶋豆は当時の全国お菓子品評会で賞を総なめにしたという、子供からお年寄りまで楽しめる飛騨駄菓子の原点ともいえる商品です。その製法には大変な手間と時間が必要で、当社では大豆の上に薄く砂糖を塗っては乾燥させるという作業を何度も繰り返して商品が出来上がります。この作業が無ければ表面のつるっとしたきれいなコーティングが作り出せないためです。私はこのような“手間を惜しまない製法”が誕生したのも高山ならではだと考えております。
そして飛騨駄菓子はお客様の声や時代に合わせて少しずつ変化してきました。 “かんかん棒”という駄菓子は水あめときな粉を棒状に固めた折れない程硬いものでしたが、時代とともにどんどん柔らかく変化してきました。しかし、ある時「これはかんかん棒ではない!」と思い、従来の硬いかんかん棒を復刻させました。今では柔らかい“きなこ棒”、昔ながらの固い“かんかん棒”と2種類販売していますのでどちらがお好きか食べ比べていただきたいです。
最後に、飛騨駄菓子は体にも優しい素材で出来ており、子供からお年寄りまで安心して口に入れて頂けます。パッケージの素材を見ていただくとほとんどの商品が“砂糖”“きな粉”“塩”“胡麻”など自然素材のものが簡単に2~3行載っているだけ。これで十分。 こういったところも魅力のひとつだと思っています。
今力を入れていることは何ですか?
おかげ様で観光のお客様や全国からのお取り寄せが多く大変ありがたいことですが、実は先般、一年を通して高山の高校生と一緒に「ももこつ」という飛騨の桃味のげんこつを開発した際、半数の生徒さんが飛騨駄菓子を食べたことが無いということを知って驚きました。私たちが力を入れなければならないのは地元の子共達にもっと飛騨高山の味を知ってもらい、それを後世に残していくことだと感じました。
具体的には地元スーパーさんの中にテナントを構えることでお店に来られる若いお母さん方に飛騨駄菓子を発信していこうと思っています。やはり地元のお菓子は地元の方に愛されて残っていくものですし、何よりも子供たちにたくさん食べてもらいたいというのが一番の願いです。
観光で高山へいらっしゃる方へ一言お願いします。
飛騨地方ならではの伝統や風習に触れられることを楽しみに観光に来てくださっている方、是非飛騨駄菓子を実際に食べてみてください。原料も製法も素朴だからこそ一切ごまかしが利かない駄菓子には、昔ながらの思いと飛騨地方の文化がしっかりと受け継がれていますよ。

飛騨駄菓子の原点
「三嶋豆」
カリカリの白い糖衣をまとった飛騨高山伝統の豆菓子です。砂糖蜜を何回も繰り返し大豆にまわし掛けることで、なめらかで綺麗な衣をつくり上げます。

打保屋の代表駄菓子
「こくせん」
「こだわりの焙煎(濃煎)で香りを最大限に引き出した黒胡麻をふんだんに使用して、水飴で煮詰めて固めた飛騨の伝統的な駄菓子です。
- 駄菓子の店 打保屋 宮川朝市店
- 住所 〒506-0841 岐阜県高山市下三之町23番地
- 0577-52-2221
- 通販ページ : http://www.rakuten.ne.jp/gold/utsuboya/

 |
|

2013年「マツコの知らない世界」(TV番組)にて飛騨のお惣菜「あげづけ」が紹介され、飛騨食材のインターネット販売を手掛けていたファミリーストアさとう様に
16万件もの注文が殺到。東京の人の反応が“これほどか”と驚いたというお話から伺いました。
飛騨食材のヒットがきっかけで『外から観る飛騨』を知りました。「なんだ、原石はここにあったのか」と、とても身近なところで宝石を見つけた気持ちになりました。
飛騨高山の魅力は?
魅力はやはり『食文化』です。TVを通して飛騨の家庭の食文化がヒットしたわけですが、あれが“作られた名物”だったら、きっとこんなにヒットが続いていないと思っています。
昔からから飛騨は“焼く”文化なんですよ。「寒い土地だから鍋では?」と思いますが、例えば、けいちゃん、漬物ステーキ、豆腐ステーキなど、実は焼くものが多い。
私が幼い頃は囲炉裏こそありませんでしたが、ストーブでは漬物を焼いたりネギを味噌で焼いたりと、とにかく全部焼いてました。飛騨には鍋に入れて炊くような食材がなく、
大豆で加工した豆腐とか漬物ばかりで、言い方は悪いかもしれないけど“粗末”だったんですよ。
例えば漬物は秋に漬けこみますが1月~2月はシャリシャリに凍っていて少し酸っぱくなっている。それを焼いて温めてから食べることでおいしくする。さらに言えば漬物を煮る『にたくもじ』というのもあります。
“限られた食材をなんとかおいしく食べるよう”と発展してきた。そんなところから飛騨の食文化は来ていると思います。それが現代まで引き継がれ、今改めて魅力に思っていただけて
いるのだと思います。決して当社が特別戦略的に仕掛けたわけではありません。今まで地元の皆様が、地元の食材を買い続けてくださっていたから地元食材の品揃えでやって来られたわけです。
そして私たちスーパーは、地元の皆様の食卓に喜んでいただけるものを提供してきただけのことでした。
そう考えると、「地元の方が喜んでくれる事」こそが、「他所からのお客様にとっても価値がある事」になっていきます。この順番は絶対に間違えないようにしています。
また、地元食材の製造メーカーさんたちのパワーは外せません。当店の場合、大手スーパーさんとは違い地元のメーカーさんが棚まで来てくださり、棚の中の売れ方など意識して品出しをしてくれます。
メーカーさんも棚を見て「今日は売れたかな~」と一喜一憂してくださる姿は“お店と一体”なんです。 こういう気持ちが本当にありがたいです。
実はね、つい最近まで手書きの伝票でしたが、去年からiPadで受発注ができる仕組みを作りました。苦手な方も苦心しながら協力して一緒に取り組んでくださるんです。
厚い信頼があるから、みなさん協力してくださるのですね?
それもあるかもしれませんが、この土地の特徴が“協力する文化”だからかもしれません。 飛騨は豪雪地のため昔から常に助け合わないと一人では生きていけない土地です。お年寄りへ声をかけ無事を確かめたり、雪かきは自分が止めると交通も全部止まってしまう。 だから“助け合う”というスピリットがどんな場合でもあると思います。「あいつがやるなら仕方ないな」という感じかもしれませんが(笑)
今一番力を入れていることは何ですか?
自分達で作る商品や製造元さんと一緒に作った商品などがある中で、商品に込められた『思い』をどんどん紹介していくことに力を入れたいです。
『売れる』というより、製造があって、売る人がいてお客様が喜んでくださる、そういう商品を提供していきたいんですよ。
例えば、何かにこだわっている農家さんがあれば、当店をそのこだわりを紹介する“場所”にすることで地元を大事にやっていきたいと思っています。
観光で高山へいらっしゃる方へ一言お願いします
飛騨の食文化を体験したければ地元密着のスーパーに寄っていただいくことが“ツウ”な観光の仕方ですよとお勧めします。高山のスーパーならではの雰囲気や山菜のような 季節限定商品の品揃えの多さ、 商品の陳列方法に工夫をしている点にも注目して頂けたら、本当の高山食材を実感して頂けると思います。これからも、より地元の食材や地域性のある 商品の品揃えをしていきますので、観光へお越しの際はファミリーストアさとうに寄っていただければ嬉しいです。

リピート率№1の
「あげづけ」
秘伝の味付けが大好評でそのまま焼くだけ。おかずはもちろんおつまみや子供のおやつにもなり高山の食卓に欠かせない一品。

ファミリーストアさとう売れ筋5大商品
「豆つかげ」
「あげづけ」
「山家のけいちゃん」
「めしどろぼ」
「飛騨清見ソース」
- 株式会社ファミリーストアさとう
- 住所 〒506-0825 岐阜県高山市石浦町2-352
- 0577(33)0622 / FAX : 0577(34)0623
- ホームページ: http://www.tokutokusatou.com
通販ページ : http://www.takayamasatou.com

 |
|

川上さんは、高山市文協会から『永年に亘る上宝を中心とした民俗・歴史研究、特に播隆上人*の研究につとめ、多数の著書を執筆された』功績を称えられ、平成27年1月に高山市文化功労者顕彰を受賞されました。
*「播隆上人(ばんりゅうしょうにん)」とは江戸時代後半、飛騨高山郷の窟で修行を積んだ浄土宗の僧で日本登山史に欠かせない人物の一人。文政6年(1823)、日本で初めて日本アルプスの槍ヶ岳の開山を成し遂げました。播隆上人は後に登ってくる人が歩きやすいように地元の信者の協力のもと鉄の鎖をかけるなど、生涯をかけて登山ルートの確保を行うなどの偉業を成し遂げましたが、いつのまにか歴史に埋もれていました。
ここ、奥飛騨・上宝の魅力は?
手つかずの大自然は本当に素晴らしい。ここにしかない植物や知られていない巨木、地図にも載っていない美しい滝も沢山ある。地理院から問い合わせがあったり滝のマニアからも教えてほしいって連絡もある。いわゆるハコモノは無いところだから、本当に美しい昔のままの日本があるところですよと伝えたいなあ。昔から道端に置かれている小さな石仏も何気なくある風景の一つなんですよ。
上宝の石仏に興味を持たれたきっかけは?
もともと多少の興味があった地元の伝統文化について何か掘り起しがしたいと思っていました。
研究を始めたのは、銀行を定年退職して次の職場の商工会に勤めていた平成10年頃からですよ。
商工会で地元のいろいろな場所を回っているうちに、ふと街道筋の露天にある石仏なら誰にも迷惑をかけなくても調べることができるなと思ったのがきっかけ。
いざやってみると、この石仏がお地蔵様なのか観音様なのか他のものなのかも分からない。日本石仏協会のお力をお借りしながら調べていると、どうしても「お宮」や「狛犬」、「お寺」とか「自然風景の渓谷」「滝」「播隆上人」などとも関連していって。そこで、石仏に限らず分かることは全部収録しながら、ということになったんですよ。
日本には石仏自体は平安時代(794年~1192年)からあるけど上宝ではそれより約900年後の元禄(1688年~1704年)くらいからやね。天保(1830年~1844年)に入ってからは天保飢饉があったから飢饉の石仏もあるね。調べたら上宝だけで全部で400体ほどあって地図に起こしましたよ。
石仏の置かれている場所は、日本で最初に槍ヶ岳の登頂を果たした江戸時代の播隆上人の足跡との関連も見つけました。播隆上人の記録はあまり知られていないんですよ。調べているうちに播隆上人がここで修行したという形跡も見つけることになっていき、その修行場所を発掘したら墨で字が書いている『経文石』が出てきましてね、地元の人は存在は知っていたようですが改めて整理して公表をしました。
経文石というのは、石(手の平に乗るほど3~4センチ)に漢字を書いてあるもので何が書いてあるのか、なかなか判別できないけど一部が『観音経』だったことを発見できたんですよ。
でも誰が書いたのかも分からない。播隆上人かもしれないし村人かも旅人かもしれない。そこはもう追いかけることができないのかもしれないですね。
自分にとっては、だれが書いたのか想像することがロマンにも魅力的にも感じますねぇ。
一番力を入れていることは何ですか?
地元の古文書の解読です。上宝郷土研究会では古文書の解読をしているんですが、所有者の方からなかなか見せてもらえない貴重なもので、自分が元気なうちにどこまで解読が進むか気になっていますねえ。それにここ上宝も日本中の他の農村地域と同じように人がどんどんと少なくなっていることが寂しい限りです。
この研究がどれほどの価値があるかわかりませんが、後の人たちや何かの研究の役にたつと良いなと思います。写真も何千枚とありますしね。
ただその写真が、3.5インチ・フロッピー・MO・スティック・CDと膨大な量があってどうしようかと困っています(笑い)。
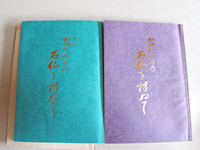
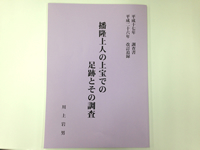

・(左)「かみたからの石仏を訪ねて」
・(中央)「播隆上人の上宝での足跡とその調査」
・(右)上宝郷土研究会の会員で同級生の大田敏多美様と一緒に
 |
|

ここ、奥飛騨の魅力は?
やっぱり、大自然かな。ここの良さは。
明治の社会教育者の篠原憮然(しのはらぶぜん)の作った歌があって、ああ偉なるかな飛騨の山、ああ美なるかな飛騨の渓(たに)、ああ清きかな飛騨の水 …と、
あるんだけど全くその通り。ここはまさに山紫水明。山から湧き出る水がきれいなところ。私はここに温泉も付けてほしかったな(笑)
3000m級の山が連なっている飛騨山脈のような風景のところは日本でも無いらしく、他には無い魅力だと思いますよ。プラスアルファで、春、夏、秋、冬と四季の変化がはっきりしていますね。
中でも春はお勧めです。他の土地に比べて期間が短いけど、春にこの場所で捕れる山菜は、こんな美味しいものは他には無いのではないかな思う位ですよ。本当に美味しいんですよ、甘味がふわっと出てきてね。
それが一年中あるわけじゃなくて本当にその一週間だけ。その時に捕ったものじゃないと旬のものが食べられないのがここの山菜。うまくタイミングをつかまないといけないですし保存は出来ないですから、貴重です。
ぜひ、体験していただきたいですね。
春は山の風情が良いですよ。春が近づくと枯れ木の枝に少しずつに芽が出始めるんです。いきなり沢山の芽は出なくて少しずつ少しずつ緑になっていく。
その様子が水彩画の山の絵のようで。最初は淡いような緑が、だんだんだんだんと濃い緑になっていく。緑もいろんな種類があるのね。その緑が折り重なったその様子がまたとても美しくて。何度体験しても、
何度見ていても本当にきれいで美しい。春は生命力というか、自然の持つ息吹を感じますよ。
何年もここに住んでいるのに、毎年感動するくらいです。
奥飛騨の春は5月10日ころから始まり、桜もその頃なんですよ。5月になったら桜を楽しみに来てください。
春はもちろんですが、冬の雪が降っている時でもすごい瞬間がありましてね。雪がピタッと止むことがあって、突然真っ青な空がぱあっと開けて、その中に真っ白な綺麗な山が見えてくる。
その時は「はぁ~っ、こりゃぁ~っ」と、思わず声がでますよ。
ここからは笠ヶ岳も見えますが、陽が沈む時に光が当たるところは白に近いようなピンクで、光の具合や山の凹凸なんかで濃いピンクもあって、濃いところは黒くなっていって、そのグラデーションが何とも言えないほど
心に迫ります。年に何回も無いんですけどね。これは、ここに住んでるものの特権かもしれないですね(笑)。たまたま出会えた人は自然からのプレゼントですよね。
奥飛騨はここでしか体験できないことや準備できないものが沢山あります。
偶然っていうか奇跡的っていうか、そういう出会いが魅力なところなんですよ。
そしてこの温泉。平湯は1300mのところにあります。こんな標高が高いところに住めるのは温泉があるからこその温泉の恵みですよね。
江戸の昔から平湯温泉は人々に知られていて多くの人が療養に訪れていた場所ですし、当時の記録にも平湯・蒲田の両温泉は残っています。それくらい素晴らしい温泉は今も変わらず溢れていますからぜひ体験していただきたいです。
今一番力を入れていることは?
ここ奥飛騨に隠れている原石、宝物・光るものがいっぱいあるということを世界へも日本の皆さんに発信していきたいです。多くの人に来てもらいたい。魅力の掘り起しと情報発信が大切ですよね。
知名度がまだまだだの部分。自分達はここに住んでいるから当たり前だと思っていたけど、東京にいったり外国に行ったりすると全然知られていないんです。
でもね、話しをすると、彼らが求めているもののベスト10中の5つか6つは必ずこの中にあるんですよ。だから彼らの求めているものの中で合致するものを「ありますよ、ここにありますよ」とアピールして、もっと知名度を高めることに力を入れています。
付録:篠原憮然「飛騨青年の叫び」
ああ偉なるかな飛騨の山 ああ美なるかな飛騨の渓 ああ清きかな飛騨の水
飛騨山脈の打つところ 剛健の意気漲りて 正義の血しお沸り湧く
緑に炎ゆる森林の 滴るところ仁愛の 花芳しく薫るなり
清泉溢れ湧くところ 気は朗らかに澄み渡り 霊智の光さゆるなし
げに限りなき天恵の 溢るる郷に生い育つ 飛騨青年の血は躍る
飛騨山郷の任重し 飛騨青年の義は重し 飛騨楽園は夢ならず』
- 岡田旅館・和楽亭
- 住所 〒506-1433岐阜県高山市 奥飛騨温泉郷平湯温泉505
- 0578-89-2336
- http://www.okadaryokan.com

 |
|

飛騨高山の魅力は?
奥深さがあるところですね。高山は、陸の孤島だったが故に古いところが残っていて、凝縮された文化を持っていると思います。
飛騨は木との生活が残っていて、ここで働く人たちの姿は更に魅力的です。夏は野菜を作っていたりする顔、木を切っている人たち、草を刈っている人たちなど、自然と共生している人たちの姿はとても良いと思いますね。
観光は、文化の土壌の上ではじめて成り立つ面があると思います。ここで働く人たちがいて文化が引き継がれていることが魅力になっていると思います。都会に出て戻ってくる人も多いですしね。
どうして戻ってきたくなるのでしょうか?
ひとつは空気じゃないかな。東京でも一日歩いて、喫茶店に入っておしぼりで顔をふくと黒くなったりするけど、山に一日中入ったってあんなに黒くならない(笑)
都会に行っていろんな体験をして、その間、我々はきちっとここの良いところを残しておけば必ず戻ってくるんです。それが観光でも魅力になっているかと思います。
高山の魅力、何度訪れても発見があるというところは?
体験していただきたいところがいくつかあります。
乗鞍岳は主峰 剣ヶ峰3026mをピークに2500m以上の標高の岳を23峰有する場所です。
高山植物や雷鳥を観ることができますし、標高2702mまで車で訪れることができるのは日本一で高山帯での貴重な体験ができますよ。
五色ヶ原の森は乗鞍火山の溶岩流が形成した台地で、比較的開発の波にさらされずに取り残されてきたために自然度の高い貴重な植生と、懐深さに由来する豊かな生態系が保たれている自然の宝庫です。
入場者数規制も設けてガイドがいないと入れないようになっていることも功を奏しています。
ほうのき平スキー場は県下屈指のスキー場で、乗鞍の岳降ろしの環境は北向きの斜面のため、良質の雪質を保ち、多くのスキーファンが集うところです。全日本スキー連盟、FIS(国際スキー連盟)公認の
コースを完備していて冬のスポーツを楽しむのには最高の場所だと思います。
丹生川町(にゅうかわちょう)という町があります。この町の生活や人、景色や農林業を営む農山村風景は、それは素晴らしいです。地元の人間でもそう思います。
ここでは自然の恩恵との共生を観ることができます。農業、林業、観光業に働く人の姿があって、出会った人と言葉を交わすと心が通じ、ホッとする町です。水、光、風、自然環境の良いことが実証されている気がしています。
本当はここに来ていただいて体感していただくと、わかっていただけるのにと思いますね(笑)。
今一番力を入れていることは?
水を守れば世界を制す、という考えで自然環境のことに一番力を入れています。飛騨高山から川が生まれます。上が荒れると下流や河口、海の植生にも影響があり、全部つながっていますよね。
私たちも含めて生を成すものすべてが自然の恩恵で成り立っています。環境の良いところは何もかもが美しいです。人も自然も。自然はすごく優しいところもあるし、
その反面、すごく厳しくなることもある。人と似ていますね。
その自然環境の恩恵と共生の価値観で誘客し、地域振興に力を注ぎたいですね。


・(左)乗鞍(お花畑)
・(右)五色ケ原の森(横手滝)
※飛騨高山写真ライブラリーより
 |
|

「子どものころね、高山市民憲章の最初に、『わたくしたちは乗鞍のふもと山も水もうつくしい飛騨高山の市民です』って書いてあって、
『本当にそうだ、山も水も本当に美しい』って心から納得したんです。心に染みて今でもそれが残っているんです」
”高山”と言う度に目を細め、高山が大好きで仕方ないことがにじみ出ている、瀬戸山えい子様にお話しを伺いました。
飛騨高山の魅力は?
私は、飛騨高山テディベアエコビレッジの他に、力車インという宿泊客の96%が外国人というB&Bを始めて21年が経ちます。
お客様が仰るには彼等がイメージする日本のすべてが高山の中にあるんですって。
実際に人口が10万人未満のこの街に内外含めて400万人以上の観光客がいらしているんです。宮川を中心に古い町並み、お寺、伝統的文化、古民家、着物姿の人に出会える、そういう環境が歩いて10~20分の範囲内に息づいていることは、高山の魅力だと思います。
もうひとつ、ある意味、国際的というか、高山の人たちって英語に慣れていますね。朝市のおばちゃんたちも毎日普通にコミュニケーションしているし、街で道を聞かれても皆さん、臆せず対応されている。この、臆せず、というとこが凄いですよね。
また古くからのものを日常的に使っているところも、文化も食事も行事もちゃんと残ってきちんと引き継がれていますしね。自然の豊かさに恵まれていて四季の移ろいがとてもきれいなところも魅力的です。
何より安全な街なんですよ。うちのお客様の置き忘れ荷物は99%出てきます。「これって誇りだな~」って思ってます。旅にしても住むにしても『安全』というのは本当に大事なこと。・・・語り切れないですね(笑)。
今一番力を入れていることは?
本当の豊かさについて日々考えています。子どもたちが豊かに育っていく社会や生活をいかに大人の私たちが作って行けるか、色々な意味で持続可能な社会作りというところにいつも関心があります。
例えばテディベアエコビレッジのミュージアムの展示はテディベアが地球を大事にしようねって言っていたり、またカフェで使っているのは地元のオーガニックの食材ですし、コーヒーやカレー等はフェアトレードのものです。生活や日々の生産活動からも、何かしら次の世代につながるようにしていけたらな、と意識しています。古いものを大事に使いたいですね。
飛騨高山テディベアエコビレッジは、カップルやお子様連れの方、お年寄りにまでとても喜んでいただいています。テディベアが可愛らしいだけではなくて、遊んでいただけるようなスペースや、家族の思い出を沢山撮影できるところもあります。楽しみながら環境のことにも触れていただければと思っています。是非みなさまでお越しください。
- 飛騨高山テディベアエコビレッジ
- 住所 〒506-0031 岐阜県高山市西之一色町3-829-4
- 0577-37-2525
- http://www.teddyeco.jp/

 |
|

「わが社のダイニングチェアが”2014グッドデザイン賞 金賞”に選ばれたんですよ」栄えある受賞に心から喜んでいるご様子の、岡田贊三様にお話しを伺いました。 「今回、グッドデザイン賞 金賞をいただいたダイニングチェアは杉を圧縮して作ったものです。 さらに今年は、わが社の職人が”現代の名工”に選ばれたんですよ」世界初の杉圧縮柾目材の技術を活用したダイニングチェアを見せていただきました。 「律令時代には(7世紀~10世紀ごろ)、それ以前から飛騨にあった優れた木工技術を利用したい大和朝廷が、飛騨から木工技術者を呼び寄せて都作りを進めていった経緯があります。都の建築物は飛騨の匠の技術で出来ているわけですが飛騨高山には都と同じような神社仏閣が沢山あります。古代は飛騨が文化の中心地で栄えていたという説があるくらいです」飛騨の奥深い歴史を熱く語られる姿から、飛騨の匠の信頼の技術を1000年以上継承している一翼を担っているという誇りを感じました。
飛騨高山のここが魅力、何度訪れても発見があるというところは?
私がお勧めするのは、高山市民がよく散歩している城山(しろやま)ですね。高山城のあった場所です。 あそこには本当に大きな木や広葉樹など沢山あり、実は南から北まで日本中の小鳥が一堂に集まる稀有な場所で最も自然豊かなところですよ。観光スポットという感じではないかもしれませんが、お時間があれば是非歩いてほしいところです。 実は高山は不思議な自然環境のところで、太平洋側、日本海側、東日本、西日本全部の分布の分水嶺のようなところ。神社も伊勢系と出雲系が分かれていて高山市内の北は出雲系が多く、高山の南は伊勢系が多い、高山の旧市街地はどちらもミックスしているという場所ということも面白いと思いませんか。 高山に来られるときに高山の歴史や文化といった側面からも見ていただけると建物なども見え方も違ってきて気づきが多いと思います。 造り酒屋がこれほど沢山あるのは高い水準の文化があったということだと思いますよ。食も本当に豊かな土地。ぜひ3回は訪れていただきたいですね。例えば今回は建築物、今回は食というようにテーマを持っていただけると良いと思いますね。
今一番力を入れていることは?
杉は素晴らしい木。国産材の杉を活用することに今最も力を入れています。 奈良の正倉院には1300年前から伝わるものが檜ではなく杉の箱に入れてあるんですよ。杉と檜は対で使うと素晴らしい効果を発揮することが分かってきています。杉はクリプトメリア・ジャポニカと言います。ラテン語で「隠された財産」という意味です。研究をすると空気の浄化、湿度の調整、抗菌性のほかにも安らぎを与える力などわかってきています。 杉の木の活用をもっと進めて良いデザインと共に杉の木の効用も研究を進めながら、良い商品を提案して気に入っていただき、長く使っていただくという良いサイクルができるようにと考えています。
- 飛騨産業株式会社
- 住所 〒506-8686 岐阜県高山市漆垣内町3180
- 0577-32-1001(代表)
- http://kitutuki.co.jp

 |
|

「高山は初めてですか?お時間ありますか。ちょっとご案内しますよ」
初めてお会いした時のこと。高山の有名な古い町並みに連れて行っていただきました。
「この四角い穴、なんだかわかりますか」と、コンクリートに空いた10センチ四方の四角形を指さしました。
「この穴は、春と秋の高山祭の時に提灯を飾るための四角い木の杭を立てるために使うものなんですよ」
「秋葉様ってご存知ですか?」次は、古い町並みの家々のひさしの上に載っている、大きなガラスケースの中にある神棚のようなものを指さしました。
「高山はね、昔から火事が多かった町で、秋葉様の信仰が深い土地なんですよ、あの神棚も火伏せの神様の秋葉様が祭られていて、地元の人が当番制で御世話をしているのよ」と古い町並みを歩きながらいろいろな「あれも、これも」をお話ししていただきました。
ガイドブックには無い高山の昔からの工夫や風習に初めての私たちはただ驚くばかりでしたが、高山の街を女将に教えていただいているうちに高山が大好きになっていきました。
「素敵な街ですね」と感激しきりの私たちを見て嬉しそうなお顔の女将がとても印象的でした。
高山のここが好き、というところはどこですか?
「飛騨高山に住んでいる人のあたたかさが大好きです」
高山のここがお勧め、というところはどんなところですか?
「高山にはじめてお越しの方なら、まずは古い街並みを散策してください。何度もお越しのリピーターさんには、ちょこっと路地に入るのをおすすめします。一本筋を変えて歩いてみるのもよいと思います。迷子になるような大きな町ではありませんからご安心ください。私も、こんなものがありますとお伝えすることも多いのですが、しゃれたお店や喫茶店があり新しい発見ができるのが飛騨高山です。また高山の朝市は、やはり必見。何度でも行ってほしい場所です。おばちゃんたちの飾り気のない飛騨弁が、とても高山らしいこととともに季節感があふれています。そして、おまけは・・千光寺。癒しの場所。私の心のよりどころでございます」
- 飛騨高山の宿 本陣平野屋 花兆庵
- 住所 〒506-0011岐阜県高山市本町1-34
- 0577-34-1234
- http://honjinhiranoya.com/





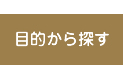

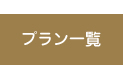
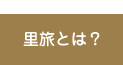
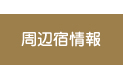

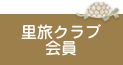
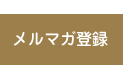
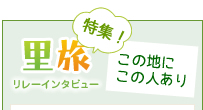




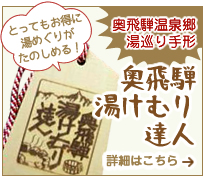


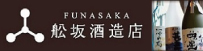



一皿ずつ日本のおもてなしの心が込められた精進料理は繊細で華やか。